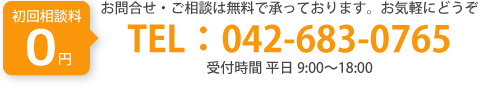双極性障害は、躁状態とうつ状態を繰り返すことで日常生活に影響が及びやすく、経済面でも負担を感じる方が少なくありません。そこで、症状によっては障害年金という公的制度を利用できる可能性があります。しかし、実際にどのような手続きを踏めばよいのか、どのようなポイントに注意すべきか、わからないことも多いかもしれません。この記事では、双極性障害をお持ちの方が障害年金を検討する際に役立つ基礎知識や申請の流れについて解説していきます。
双極性障害(躁うつ病)とは?

双極性障害は、躁状態(ハイテンションで活動的)と、うつ状態(気分の落ち込みや意欲の低下)が周期的に入れ替わる特徴があります。従来は「躁うつ病」と呼ばれることもあり、気分や行動面の変動が大きく日常生活への影響が生じやすい病気です。症状の程度や持続期間は人によって異なり、躁状態では過度な自信や活動性の高まりが見られる一方、うつ状態では意欲の喪失や悲観的な思考に陥ることがあります。双極性障害の症状は、職場や家庭などの生活環境に大きく関わってくるため、医師の診断と適切な治療、さらには周囲の理解とサポートが欠かせません。
双極性障害で障害年金を受給するための認定基準・条件は?

双極性障害における障害年金の認定基準・条件は、他の障害年金の申請と同様に、主に下記のポイントを満たしていることが求められます。
1. 初診日要件
双極性障害で医療機関を初めて受診した日(初診日)を特定することが必要です。これは障害年金の審査において重要なポイントとなり、後々の手続きや診断書の作成に大きく関わります。たとえば、初診時に利用していた病院が現在は閉院してしまっている場合など、カルテや診療録が見つからないケースもあるため、受診歴が分かる資料を早めに整理しておくと手続きが進めやすくなります。
初診日が特定できないと、書類申請や審査で不備として指摘されることがあるため、診断書を作成する医療機関にも協力を求めながら確認を行うことが望ましいとされています。仮に、最初に受診した病院の資料がない場合でも、転院先の病院で初診日を推定できる記録が残っていれば活用できる可能性があります。
2. 保険料納付要件
障害年金は、国民年金や厚生年金といった社会保険制度の枠組みの中で支給されるため、初診日の前日時点で一定期間の保険料を納めていることが求められます。具体的な期間は法律で定められており、たとえば初診日の前日に遡って一定年数分の保険料を納付または免除措置を受けていることなどが条件となります。
この要件を満たしているかどうかは、年金事務所で記録を照会したり、手元にある年金定期便などの情報を確認したりすることで把握できます。学生時代や無職期間が長かった場合などは、保険料納付要件を満たしているかどうか不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、免除制度や猶予制度を利用していた場合でも要件にカウントされるケースがあります。状況に応じて確認することで、適切な対応を図りやすくなります。
3. 障害認定日要件
双極性障害によって障害年金を受け取る場合、初診日から一定期間(通常は1年6か月)経過後に「障害認定日」が設定されることが多いです。この障害認定日における症状の状態が、障害年金の支給に値するほど重いものかどうかが審査されます。症状の重さを裏付けるために、医師の診断書や通院歴などが必須となりますが、双極性障害は気分の変動が激しい特性があり、書類上の記載だけでは把握しきれない部分もあるため、普段の生活上の困りごとや症状の経過を正確に伝えることが大切です。
さらに、障害認定日を過ぎても症状が回復せず、同等の状態が継続している場合は、事後重症という形で後から請求ができる可能性もあります。ただし、それぞれの状況によって手続きの方法や必要書類が変わるため、主治医や年金事務所へ相談しながら進めると安心です。
4. 障害の程度(等級)
障害年金の審査では、双極性障害による生活面や就労面の支障度合いを総合的に判断し、該当する等級が決定されます。双極性障害は、躁状態とうつ状態が繰り返されるという特性上、症状の波が大きく、日常生活全般や対人関係、就労状況など多方面にわたって影響を及ぼしやすい傾向があります。そのため、診断書においては医師が把握している限りの症状の推移や行動、治療歴などをしっかり記載してもらうことが重要です。具体的な等級は以下の通りです。
| 等級 | 説明 |
|---|---|
| 1級 | 日常生活全般で常時介助や援助が必要になるほど、社会的機能が大幅に低下している状態を指します。たとえば、意思疎通が難しく、入浴や食事などの身の回りの動作を自力で行うことがかなり厳しい場合などが挙げられます。 |
| 2級 | 日常生活の多くの部分で補助が必要になる状態を指します。外出や家事、対人関係などさまざまな場面で支援を受けないと生活を維持するのが困難な場合や、就労形態が制限されるほどの症状が続いている場合が該当する可能性があります。 |
| 3級 | 1級・2級ほど重度ではないものの、業務内容に配慮が必要になったり、職場や日常生活において一定の制限が生じたりしているケースで考慮されます。たとえば、就労時間の大幅な短縮や仕事内容の変更が不可欠になっている状況などが該当例として想定されます。国民年金には3級という区分がないため、3級に相当する障害が認められたとしても、国民年金のみに加入していた方は対象とならない点に留意が必要です。 |
双極性障害で障害年金を申請する方法

実際に申請を行う際には、書類の準備や医療機関との連携など、複数のステップを踏む必要があります。ここでは、双極性障害による障害年金申請の一般的な流れとポイントを解説します。
1. 初診日の特定と書類の整理
障害年金の審査では、「初めて双極性障害として受診した日(初診日)」が非常に重要な基準となります。まずは、過去の受診歴を振り返り、初診にあたる病院やクリニックを確認しましょう。
- カルテや診療録の所在確認
初診日を証明するためには、該当の医療機関に残っているカルテや診療録が必要です。すでに閉院していたり、転院していたりする場合でも、他院への紹介状などから初診日を類推できる場合があります。 - 経過を整理するメモの作成
申請時には、どのような経過で病院を転院したか、症状がいつからどの程度続いているか、といった情報を求められることがあります。事前にメモを作成しておくとスムーズです。
2. 保険料納付状況の確認
障害年金は、公的年金制度を活用して支給されるものであるため、保険料の納付状況を満たしていなければなりません。具体的には、初診日の前日に遡って一定期間の保険料を納付しているか、あるいは免除や猶予を受けているかなどが問われます。
- 年金定期便や年金記録の入手
年金事務所や自宅に送付される年金定期便などから、自身の納付状況を確認できます。疑問がある場合や書類が手元にない場合は、最寄りの年金事務所で照会が可能です。 - 免除・猶予歴の確認
学生のときや経済状況が厳しい時期に、国民年金保険料の免除や猶予を受けていたことがある場合も、一定の要件を満たせば納付要件を満たしているとみなされるケースがあります。自分がどの時期に免除を受けていたのかを把握しておきましょう。
3. 障害認定日の確認と診断書の準備
初診日から一定期間(通常1年6か月)経過後に、「障害認定日」として症状の状態が評価されます。この日を基準として、障害の程度に応じた年金の支給が検討される仕組みです。
- 障害認定日付近の診断書
障害年金の申請には、医師が作成する診断書が欠かせません。実際の障害認定日やそれ以降の症状を正確に反映してもらう必要があるため、主治医との相談が大切です。 - 事後重症の場合の対応
障害認定日よりも後に症状が重くなった場合でも、事後重症というかたちで申請が可能な場合があります。書類の提出タイミングや必要書類が変わるため、事前に年金事務所や専門家に相談してみると良いでしょう。
4. 申請書類の作成・提出
双極性障害による障害年金を申請する際には、以下の書類が代表的なものとして必要になります。ただし、個人の状況によって追加書類が必要になることがあるため、提出前に再度チェックすることが大切です。
- 年金請求書(障害年金用)
申請者の基本情報や年金の種別(国民年金・厚生年金など)を記入する書類です。 - 診断書
主治医に作成してもらう書類で、症状の程度や発症の経緯、治療方針などが記載されます。躁状態とうつ状態、それぞれの症状の特徴や日常生活への影響がわかるように記載してもらうと、審査が円滑に進みやすくなります。 - その他の添付書類
初診日証明としての受診状況等証明書や、年金手帳、戸籍関係の書類などが必要になることがあります。本人の状況によっては、障害認定日に関する補足資料などを提出する場合もあります。
5. 審査から決定までの流れ
申請に必要な書類をそろえて年金事務所へ提出すると、年金機構が書類審査を進めます。書類内容の確認や、必要に応じて追加書類の提出が求められることがあるため、連絡にはこまめに対応できるように準備しておきましょう。
- 書類補正や追加提出
提出書類に不備や不足が見つかった場合、年金事務所から通知が届きます。案内された期限内に不足分を補完しないと審査が止まってしまうため、速やかに対応することが望ましいです。 - 審査結果の通知
書類審査が終わると、障害等級と支給が認められるか否かに関する決定が通知されます。届いた結果や等級に疑問点がある場合は、専門家に相談して再度手続きを検討するという方法もあります。
6. 主治医や専門家への相談の大切さ
双極性障害は、躁とうつが繰り返されるため、症状の記載が一面的になりがちです。医師としっかりコミュニケーションをとり、実際の生活でどのような困りごとがあるかを具体的に伝えることが重要です。また、障害年金の手続きは複雑で、必要書類や証明内容が多岐にわたります。社会保険労務士などの専門家に相談することで、スムーズに進めやすくなるでしょう。
双極性障害で障害年金を申請する際の注意点
双極性障害による障害年金を検討・申請する場合、制度特有の審査手順や書類要件に加え、病状の変動が大きい点を踏まえた準備が欠かせません。ここでは、申請を進めるにあたって特に押さえておきたい注意点を詳しく解説します。
初診日の特定とカルテの確保が最優先
障害年金の審査では、はじめて双極性障害の症状を訴えて受診した日(初診日)の証明が必須となります。
- 受診状況等証明書やカルテの所在確認
最初に受診した医療機関にカルテや診療録が残っているかどうかを早めに確認しましょう。転院や閉院などでカルテの入手が難しい場合でも、紹介状や他の病院での診療記録から初診日を推定できることがあります。 - 紛失リスクへの備え
医療機関によってはカルテの保管年数に限りがあるため、受診から時間が経っている場合は注意が必要です。可能な限り早めに動くことで、初診日の証拠を確保しやすくなります。
症状の変動を正しく伝えるための工夫
双極性障害は、躁状態とうつ状態が繰り返される病気です。申請時に必要な診断書では、その変動によって日常生活に生じる困難を正確に示すことが重要です。
- 定期的な通院と症状のメモ
病院で主治医に会う際は、躁状態の時期やうつ状態の時期、具体的な行動や気持ちの変化をメモしておくと、診断書の作成に役立ちます。主治医も客観的な情報を基に状態を把握しやすくなるでしょう。 - 治療内容や服薬状況の報告
どの薬をどれくらいの期間服用したのか、また治療方針が変わった経緯なども記録すると、診断書記載時の参考情報として有益です。
診断書の内容をチェックする重要性
障害年金を審査する際、最も重視される書類が診断書です。双極性障害は気分の波が激しいため、日常生活への影響を正確に示せるよう記載してもらう必要があります。
- 日常生活活動と社会的参加の難しさを具体化
たとえば、うつ状態で起き上がることが困難になる、家事を続けられない、躁状態で衝動的に行動してしまうなど、具体的な生活上の困りごとを主治医にきちんと伝えましょう。 - 専門家による確認
主治医が書いてくれた診断書を受け取ったら、誤字脱字や日付の矛盾がないか確認することをおすすめします。必要に応じて社会保険労務士などに見てもらうと、不備を早期に発見しやすくなります。
保険料納付要件の確認
障害年金は、基本的に国民年金や厚生年金の保険料を所定の期間分納付(または免除・猶予)していることが支給の条件となります。
- 年金定期便で納付履歴を把握
手元に年金定期便がある場合は、保険料の納付状況を確認できます。もし記録に誤りがあると感じた場合は、早めに年金事務所で記録の照会をしてもらいましょう。 - 免除・猶予期間の取扱い
経済状況などで保険料が免除・猶予されていた期間があっても、一定の条件を満たしていれば要件をクリアしている可能性があります。対象期間をきちんと整理しておくと安心です。
当センターでの双極性障害での障害年金受給事例
当センターで実際に双極性障害での障害年金受給事例をご紹介します。
概要
50代 女性
病名:双極性感情障害
結果:障害基礎年金2級
依頼者の状況
Tさんは、現在52歳で、幼少期から父親の虐待を受けていたため、精神的ストレスを抱えている状態で日常生活を過していました。
その後も精神的なストレスが続いたため病気を治そう思い自宅近くの病院を受診した結果、双極性感情障害と診断され、現在2週間に1回の頻度で通院し精神療法及び薬物療法を続けていました。
そして病院の主治医から障害年金の制度を教えられたため、自分の病状でも障害年金の申請ができるのかどうかを相談したいと考え多摩・八王子障害年金相談センターに相談することにしました。
受任から受給まで
Tさん本人と面談し病状をヒヤリングした結果、治療に努めるものの症状に波があるため、食事や掃除・洗濯などの家事もできない状態で基本的な日常生活を過ごすことができなくなっていることが伺えました。
そして現在は夫のサポートがないと日常生活を正常に送ることが出来ない状態だったため、Tさんに障害年金を受給できる可能性がある旨を伝え、申請書類を揃えて提出した結果、障害基礎年金2級が認定されました。
まとめ
双極性障害に関する障害年金申請では、書類の準備や医師の診断書など、押さえるべきポイントは多岐にわたりますが、一つひとつ確認して進めることが大切です。不安や疑問がある場合には、専門家へ相談することで、より安心して制度を利用できるようになるでしょう。
多摩・八王子障害年金相談センターでは電話やメールで相談いただくことが可能です。障害年金のことでお悩みがあればぜひお気軽にご相談ください。
小野 勝俊
最新記事 by 小野 勝俊 (全て見る)
- 反復性うつ病で障害年金はもらえる?受給の3条件と申請の流れ - 2025年12月26日
- 年末年始休暇のお知らせ - 2025年11月30日
- 障害年金がもらえない人のよくある勘違い3つと対処法 - 2025年09月29日
- 夏期休暇のお知らせ - 2025年07月10日
- 人工透析で障害年金はもらえる?申請前に知っておくべき3つポイントについて専門家が解説 - 2025年07月07日